産業や実社会に根ざしたAI技術で日本を元気に!
産業や実社会に根ざしたAI技術で日本を元気に!
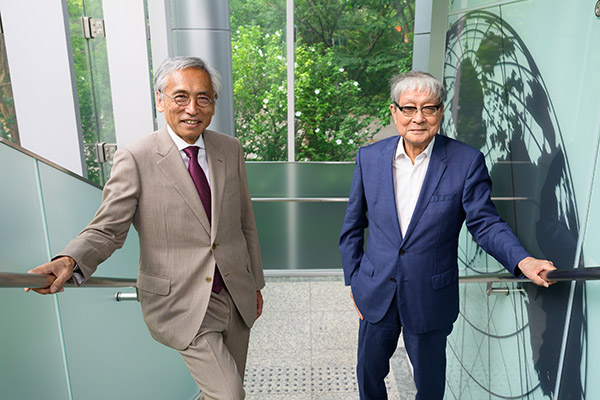
2025/11/19
産業や実社会に根ざしたAI技術で日本を元気に! 二人の人工知能研究センター長に聞く AIRCの10年と、これから

 人工知能研究センター(Artificial Intelligence Research Center, AIRC)は、日本のAI研究開発の中核拠点として設立され、2025年5月に10周年を迎えた。この10年間でAIを取り巻く環境は激変し、研究開発の手法はもちろん、産業界や生活者とAIとの関わり方も大きく様変わりしている。設立当初から2023年までセンター長を務めた辻井潤一フェロー、そして現在AIRCを率いる片桐恭弘研究センター長の二人に、AIRCの10年を振り返ってもらいながら、日本の産業や社会の持続的成長においてAIが果たすべき役割について話を聞いた。
人工知能研究センター(Artificial Intelligence Research Center, AIRC)は、日本のAI研究開発の中核拠点として設立され、2025年5月に10周年を迎えた。この10年間でAIを取り巻く環境は激変し、研究開発の手法はもちろん、産業界や生活者とAIとの関わり方も大きく様変わりしている。設立当初から2023年までセンター長を務めた辻井潤一フェロー、そして現在AIRCを率いる片桐恭弘研究センター長の二人に、AIRCの10年を振り返ってもらいながら、日本の産業や社会の持続的成長においてAIが果たすべき役割について話を聞いた。
産業界や社会の実課題を解くAIの開発を目指す
――産総研は2015年5月に人工知能研究センター(AIRC)を設立しました。設立時点でAIRCに込めた思いはどのようなものでしたか。
辻井2012年頃からディープラーニング(深層学習)の活用が世界的なブームになり、日本もAIに力を入れる必要があるという風潮が生まれました。そうした中で、経済産業省が所管する産総研に人工知能の研究センターを作ることになりました。
当時、研究センター長として考えたのは、「日本はどのような立場でAI研究に取り組むべきか」ということでした。これは今でも変わりませんが、資本力や計算資源、膨大なデータを有するアメリカの巨大IT企業が、この分野をリードしているのが現実です。そうした最先端技術の動向をフォローしつつも、日本ならではの特徴をどのように出していくかが問われていました。日本の状況をあらためて見直してみると、あらゆる産業分野において、世界的にも高い競争力を持つ企業が数多く存在しています。そうした日本の産業をさらに強くしていくためのAI――それこそが、私たちが目指すべき方向ではないかと考えたのです。AIRCは、そのような産業との連携を重視し、「日本発の価値あるAI技術の創出」に取り組むことにしました。
巨大IT企業は、どちらかといえばサイバースペースの中に閉じた、マスマーケット向けのAI開発に注力していました。それに対して日本では、より現実の産業界や社会課題の解決に資するAIの実現を目指そう――そうした方向性で取り組んでいこうという流れがありました。私自身も当時から、このような考え方を「実世界AI」という言葉で強く主張してきました。
――「実世界AI」を実現するために、AIRCには人材も必要だったと思います。
辻井巨大IT企業は、エンジニアも研究者も、優秀な人材をかなり集めていました。AIRCでも将来のAIの開発を考えると、人材も含めてリソースを集中する必要があります。日本にも優秀な研究者は多くいますが、財政の問題もあり、人を集めるといっても限界があります。その上、優秀な研究者は大学や企業などに分散しているため、個々の規模は小さく、巨大IT企業のような大掛かりな研究ができません。
それならば、大学を含む日本の優秀な人材に、「ネットワーク型」で産総研に来てもらってはどうか。AIRCが人材をネットワーク型につなげて研究の輪を広げていくことで、センター運営をしていく方向性です。さらに日本は、アメリカほどではなくても、ドイツやフランスなどと並んでAI研究で世界をリードする国の一つであり、海外とのネットワークの重要性も感じていました。産総研が、国内外の人材をネットワーク型でつなぐ拠点になって、「実世界AI」の研究開発を進めようと考えました。
理論と計算機科学の融合から産業との連携へ
――幅広い人材と連携しながら「実世界AI」の研究開発を進めるにあたり、AIRCの強みは、どのような点にあったといえますか。
辻井AIRCの設立当時、数理理論に特化した機械学習の研究開発は終息に向かっていると考えていました。AIは、インフラ設計も含めた計算機科学と数理理論の双方が融合して進化していくものへと変化していました。実際問題として、産総研は大学や他の研究機関と比べて、数理理論に強みを持つ研究機関ではありません。一方で、計算機科学や多くの産業との連携研究では実績がありますから、計算機科学と数理理論の境界の領域に取り組むのが自然でした。
計算機上で現実世界を模倣するシミュレーションや、知識・情報をグラフ構造で表現するナレッジグラフなどをAIと組み合わせることで、現実の課題を解決していこうというのが、私たちの考え方です。現実の課題には、さまざまなセンサーが生成するデータを「入口」とし、その「出口」としては、自動運転やロボットといった行動主体によるソリューションが位置づけられます。AIRCが目指すのは、こうした「現実世界とつながるAIの構築」であり、単にサイバー空間に閉じたAIではありません。産業との架け橋となる領域は、もともと産総研が伝統的に強みとしてきた分野であり、同時に、それは日本の産業構造そのものが持つ特徴でもあります。
――片桐研究センター長は、当時は大学に所属されていました。外部から、AIRCの設立をどのように見ていましたか。また、どのような印象を持っていたのでしょうか。
片桐機械学習などのAIモデルの研究開発は、資金力がないと突き進めません。私自身も数理理論的なAIの研究には進みませんでした。また、産総研は経産省傘下ということもあり、AIRC設立当時から、産業との連携の方向に進んでいくことが自然だと考えていました。

「もぐらたたき」ではなく「横展開」できるAIへ
――AIRCで研究開発が始まってから10年が経過しました。その間、AIのトレンドをどのように見てこられましたか。
辻井AIRC設立からしばらくの間、特に感じたのは、当時のAI技術が「個別的になってしまう」ということでした。「この問題を解くためのAI技術ができました」ということが、問題ごとに起こっていたのです。要するに、多くの問題をもぐらたたきのように一つずつ潰していくAI開発が行われており、これはつらい取り組み方だと感じていました。
そこで着目したのが、汎用的な問題を解決できる基盤モデルでした。OpneAIがChatGPTを発表する前から、GPT(Generative Pre-trained Transformer)のPに相当するPre-Trainedモデルを使った基盤モデルの開発に取り組んでいたのです。
2020年からの研究の柱として、基盤モデルである「容易に構築できるAI」の開発にも取り組みました。個別の課題を解決するAIを作りながら、その際に横展開できるような方法論を取り込んだものです。もぐらたたきではなく、多様な用途に使えるAIというわけです。ChatGPTは、テキストをたくさん学習させて驚異的な成果を上げましたが、AIRCでも画像や音声、ロボティクスのデータなどを学習させて基盤モデルを作ることを、一つの柱にしたのです。*1ここでも、「実世界AI」へのAIRCの取り組みの方向性が感じられると思います。
――「実世界AI」を考えると、ロボットや産業機器などだけでなく、AIと人間との関係も考える必要がありそうです。
辻井特にヨーロッパを中心に、「ヒューマンセントリックAI(人間中心のAI)」という考え方が注目されるようになりました。AIRCでも、人間とAIの関係性として、互いに高め合いながら作業を行う「協調型AI(Collaborative AI)」を提唱してきました。単に人間とAIが並列で作業するのではなく、もう一歩進んで、互いの能力を相互にやり取りし、共に向上していけるような関係性を模索したのです。
技術的には、AIの判断に人間が関与する「ヒューマン・イン・ザ・ループ(Human-in-the-Loop)」の考え方に基づいていますが、そこに専門家が加わることで、人間側のスキルも向上し、同時にAIモデルの性能も高まる――そうした双方向的な成長を実現する枠組みが必要になります。例えば、医療であれば医師や看護師、製造業であれば熟練工や設計者といった専門家に関与してもらい、人間とAIがそれぞれの強みを生かして協調していくのです。この「協調型AI」の構想は、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のプロジェクト*2としても採択され、5年間にわたって本格的な研究開発に取り組むこととなりました。
――AIの研究開発に、他分野の専門家が関わることについて、どのように考えますか。
片桐私の専門である人間・機械コミュニケーションの分野では、機械学習やディープラーニングの進歩で飛躍的に性能が向上しました。AIの進歩により、応用の可能性が広がり、容易にAIが活用できるようになってきました。そうしたフェーズでは、AIの専門家だけが性能を追求しても、世の中への応用が進みません。世の中で適切に使うことで価値が生まれるので、現実世界の専門家の知見は不可欠なのです。
その上で、ヒューマンセントリックAIの考え方が重要です。人間と対立しないAI、人間に怖がられずに役に立つAI、納得して一緒に使えるAIが求められていて、AIRCでも研究開発を進めています。今後、AIRCが研究開発しているヒューマンセントリックAIの強みが出てくると思います。
AIの浸透とユースケースの広がりに期待
――2025年現在、AIはさまざまな用途で現実世界に広がりつつあります。課題に感じていることはありますか。
辻井AIはすでに、社会のさまざまな場面に浸透し始めています。一方で、AIがなかった頃の社会システムと合致しない点も生じてきていると思います。これは技術的な問題でもありますが、社会システムの問題、ユーザーの受け取り方の問題なども絡み合ったものです。もはやAIは、「箱の中のモノ」ではなく、社会の隅々と関わりを持ち始めているからです。
片桐製造業、サービス業、金融業など、多様な業種において、AIの導入が進んでいます。産総研は、「産業・現場に近い研究」を行っています。それだけに、ユースケースとして実際に使うとどのような効用があるかを特に注視しています。理論的には問題がなくても、現場で使うと問題は必ず現れます。そこを確認しながら対処していけるのがAIRCです。
――現実世界の問題に対して、解決の具体的なイメージを教えてください。
辻井産総研は、多くの産業領域と接点を持ち、ユーザー企業とのパートナー関係も築いています。こうした中で、現実世界の課題を解決するだけであれば、各企業が自社で取り組めばよい、という考え方もあるでしょう。しかし、それでは先ほど述べた「基盤モデルの横展開」という考え方とは一致しません。AIRCの役割は、個別の問題を解くことにとどまらず、その過程で「どのように解いたのか」という方法論を抽出し、汎用化・一般化していくことにあります。つまり、「できてよかったですね」で終わるのではなく、「なぜそれがうまくいったのか」を明らかにし、それを次の課題解決や産業応用へとつなげていく――それこそが、AIRCの、そして国の研究機関としての本来の使命だと考えています。
AIが完全なブラックボックスだった場合、ほぼ正しい答えを出してくるとしても、現実世界では使いにくいものです。例えば医療に応用する時、AIの説明性は不可欠です。どこまでAIを透明化できるか、コントローラブルにできるかは、AIRCが研究することの意義の一つ。一方、医療でAI説明性を研究すれば、それは製造業などでも使える技術になります。現実世界のタフな問題を解きながら、横展開して使っていける基盤モデルを作ることが大切です。
――現実世界でのAIの活用が、どのように広がると感じますか。
片桐これまでの文脈から、あえて少し外れたことをお話します。コンテンツ産業では、クリエイターがAI活用を嫌う傾向があります。画像生成にせよ、文書生成にせよ、「自分たちの既得権益のある領域を侵される」と考えるためです。しかし、そこでAIと人間が対立するのではなく、AIと人間が「一緒に制作しましょう」といった形で、AIをツールとして活用する方法もあるはずです。AIをツールとして突き詰めることで、作業的な部分はAIに任せて、人間のクリエイターは、自分ならではのクリエイティブに集中するという考え方です。漫画家の仕事でも、作業的な部分は多いと聞きます。生成AIに作業を手伝ってもらえば、漫画家としての生産性が上がるかもしれません。医療や製造業などを中心に産業の話をしてきましたが、毛色が異なるコンテンツ産業でも、AI活用の幅が広がっていく可能性があるのです。
「AI for Science」という考え方もあります。材料科学でバイオ物質を作ったり、薬を作ったりする時に、シミュレーションとAIをつなげて高い効用のある新しい物質を探し出すようなAI活用法です。これも、現実世界とのAIの重要な関わり方です。AIRCだけでは、こうした現実世界の課題の解決はできませんから、それぞれの分野の専門家とコラボレーションしていくことの必要性を感じています。
「プラント制御」「FDSL」などにAIRCの研究の成果
――実際にAIRCで生まれたAI技術の中で、AIRCの研究開発の特徴が現れていると感じられるものを教えてください。
辻井個人的に好きなのは、NEC連携ラボ(NEC-産総研 人工知能連携研究室)の成果で、シミュレーションとAIを活用した化学プラントの制御です。既存の制御理論とは異なる観点でAIが役立つものです。シミュレーターを使って強化学習*3することで、プラント制御にAIが使えることを実証しました。実用化が進んでいますし、理論的にも面白いものです。
もう一つ挙げると、画像関係の基盤モデルの研究です。数式でデータを作って基盤モデルを作る研究で、「FDSL(Formula-Driven Supervised Learning)」と名付けられています。イメージネットのように既存の画像から基盤モデルを作るのではなく、数式で作成した図形から事前学習することで、基盤モデルを作ることができます。(産総研マガジン「日本発、最高精度の画像認識AIを誰でも実現可能に!」)

片桐FDSLは、産総研独自のものとして推している技術です。産業のアプリケーションに加えて、サイエンスのアプリケーションでも使える幅広い用途が考えられます。数式を使って作った図形だけでなく、より抽象化した人工的な合成データも使うことで、かなり少ないデータで機械学習ができる技術であり、ポテンシャルは高いです。(産総研マガジン「「物流自動化の課題」に挑む豊田自動織機と産総研」)
個人的には、「AIと人間が相互に提示する技術」に注目しています。これは、協調型AIの考え方とも関係しており、NEDOの「実世界に埋め込まれる人間中心の人工知能技術の研究開発」プロジェクトの成果の一部として取り組まれたものです。例えば、医療画像を見て特定の病気を判断することは、すでに基盤モデルでも可能になっています。しかし、AIが一方的に「病気です」「問題ありません」と診断しても、そこに人間が納得できる根拠が伴わなければ、医療現場では信頼されません。そこで、AIの診断結果を医師にフィードバックし、医師とAIが対話を通じて判断根拠をすり合わせるような仕組みが求められています。AIは人間から根拠を学び、判断の精度と説明力を高めます。この仕組みは、AIの成長を促すだけでなく、医師ごとの判断のばらつきを平準化することにもつながる重要な技術であり、今後の展開に大いに期待しています。
辻井「プロフェッショナル・イン・ザ・ループ」として、専門家をAIシステムに組み入れるよい例です。これまでのAIは、正解があるデータを集めて学習させました。しかし、医療は症例のデータも少なく、正解が作りにくい分野です。医師によって着眼点も異なります。そうした状況で、医師という専門家をAIのループに取り込んで、AIを介して医師全体の知識を共有する仕組みを作ります。AIが人間の知識とつながっていくので、協調型AIの具体例として、大変価値がある研究です。(産総研マガジン「医療AIとは?」)
片桐人間とAIのコラボレーションを考えた時、人間がすべてを仕切ることはだんだんと難しくなり、AIに決定権を渡す場面も増えていくでしょう。そうした時、人間とAIの間には、ある種の信頼関係が必要になります。協調型AIが社会実装され、人間が気づかなかった観点をAIが提示することで、AIへの人間の信頼感が高まっていく将来に期待しています。
AIRCだからできる多彩なコラボレーション

――現・前研究センター長として、AIRCの特長をあらためて教えてください。
辻井大学と比較すると、予算も豊富で専門家が参集していて、スケール感のある研究ができるところが魅力だと思います。また、大学機関からも垣根なく参加してもらえます。民間企業の研究所では、どうしてもマーケットを意識することになりますが、AIRCでは基盤的な研究や社会に貢献できる研究がスケール感を持ってできます。AI研究には適した環境だと思います。
片桐AIRCという組織の特長を表す一つのアナロジーとして、「リサーチ・ユニバーシティー」があります。教育はせずに、研究に特化した大学機関です。企業の研究所とは異なり、利益につながらない研究もできる環境です。AIRCは、リサーチ・ユニバーシティー的な側面を持ちながら、一方で「産業・現場寄り」の研究もできます。双方の側面から、世の中に役立つ成果を生み出すという方向性を持った、珍しい研究所であることが特長だと感じています。
辻井日本の社会には、いまだに高いレベルの知的基盤があると感じています。今後は、社会全体が持つ知的な力が、AIに集約されていく時代になっていくでしょう。そうした時代では、産総研のような公的研究機関が、単なる利益追求にとどまらず、社会に分散して存在する知を集積し、活用していく「知のハブ」として、大きな意味を持つと考えています。AIが、社会の強さに直接的に貢献するようになっていく中で、日本が持つ知的資源――例えば医療、製造業、インフラなどに蓄積された専門知とAIとがうまく融合し、全体として国全体の力を底上げしていくような未来を期待しています。
日本には、分野横断的に豊富な知的リソースが蓄積されています。それらをAIと結びつけてさらに強くしていくようなストーリーを、AIRCが先頭に立って描いていけると理想的ですね。
*1: 産総研AIRCの開発成果には、大規模言語モデル、日本語音声基盤モデル、 医療分野の画像基盤モデルなど多様な基盤モデルがある。[参照元へ戻る]
*2: NEDO 「人と共に進化する次世代人工知能に関する技術開発事業」 [参照元へ戻る]
*3: 強化学習:AIが試行錯誤を繰り返して、最適な行動を学習する機械学習の一種)[参照元へ戻る]
情報・人間工学領域
フェロー
辻井 潤一
Tsujii Junichi
人工知能研究センター
研究センター長
片桐 恭弘
Katagiri Yasuhiro