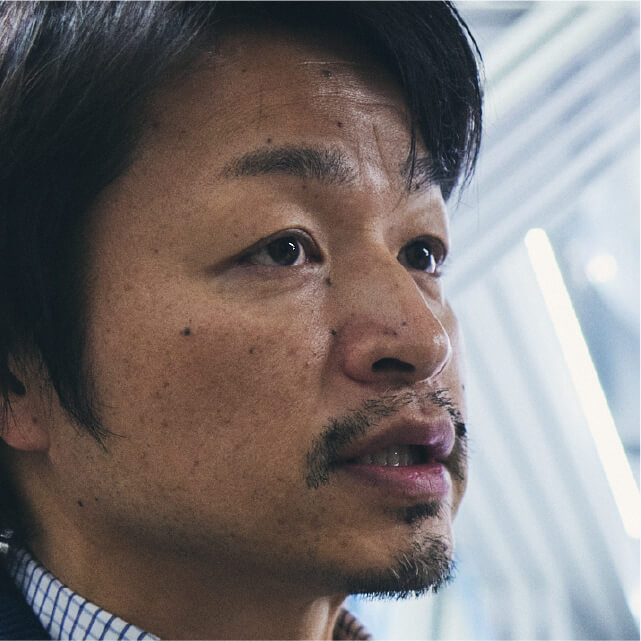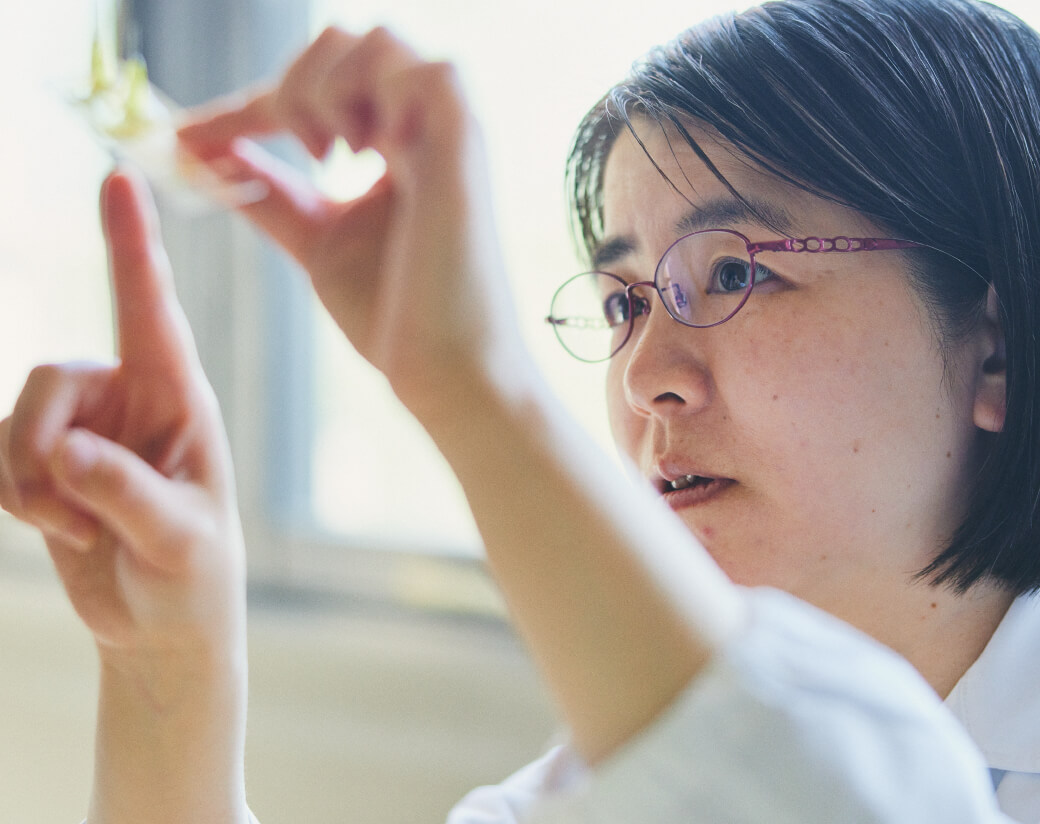産総研より先に、
量子研究を始めていた
子どものころは生物学者になるのが夢でした。田舎育ちということもあり、毎日のように川釣りや昆虫採集をしていたものです。身の回りにあった生きた素材を用いて、仮説を立て実験し、実証を繰り返していました。今思えば、ここが研究者人生のスタートラインかもしれません。中学生の時にはもう「博士号を取りたい」と考えていました。
その後、高専の電気工学科に進学し、大学の工学部3年次に編入。学部4年と修士課程では高温超伝導体材料のデバイス応用に関する研究をしていました。電流というマクロな量ではなく、それの元となるミクロな電子(=量子)の量子トンネル現象(単一電子トンネリング)に興味を持ったのも、そのころです。当時の講義で、量子コンピュータの最小構成要素となる世界初の超伝導量子ビットに関する学術論文を読む機会があり、「高温超伝導体で量子ビットが実現できないか?」と考えました。そこで所属研究室の教授にお願いして、博士課程の研究テーマを「高温超伝導体を用いた量子ビットに関する研究」にしてもらいました。まだ今ほど「量子ビット」や「量子コンピュータ」という言葉が一般的になる前。超伝導体を用いた量子コンピュータの研究を行っている拠点が、日本に2カ所しかなかった時代です。
博士課程修了後は、その数少ない研究拠点の一つである公的研究機関で、研究員になりました。それから10年ほど経ち、世界的に量子コンピュータが盛り上がりはじめます。産総研もいよいよ量子コンピュータに関する研究を始めることになり、研究者の公募が始まりました。当時、私は30代後半。この研究分野のパイオニアである上司、同僚や共同研究者と素晴らしい研究環境で研究を続け、気づけば11年ほどの時間が経過していました。ちょうどその頃取りかかっていた研究テーマで論文を書き上げ、次のキャリアを考えるにはいいタイミングでもありました。産総研には新しい実験装置が導入されるという話を聞き、公募への応募を決断しました。